知っておくともっと楽しい?パーティー雑学あれこれ
「パーティー」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは華やかな衣装、美味しい料理、優雅な音楽、そして笑顔にあふれた時間でしょう。
しかし、こうした社交の場には長い歴史があり、世界各国で独自の文化やマナー、習慣が育まれてきました。
今日は、パーティーの起源や世界の文化、知っておくと役立つ(かもしれない?)雑学などをご紹介いたします。
知識を少し加えるだけで、次の集まりがもっと楽しく、印象的になるかもしれません。
目次
パーティーは、こうして始まった
一般的にパーティーと聞くと飲食を伴う「宴会」をイメージされる方も多いかもしれません。
こうした「パーティー」の起源は、古代ローマやギリシャの時代にまでさかのぼるとされ、当時の言葉で「コーミッサーティオ」や「シュンポシオン」と呼ばれていました。
どちらも宴会を意味する言葉であり、これらは主に飲食を通じて社交を深める場であったといわれています。
また、音楽や詩(うた)の存在も非常に重要であり、美味しい食事やお酒と共に参加者はリラックスしながら交流を楽しんだそうです。
中世ヨーロッパでは、王侯貴族による「晩餐会」が発展し、より形式的かつ豪華になっていきます。
この頃から、厳格なテーブルマナーや服装の規定が整備されるようになり、現代のパーティーへと繋がっていくこととなります。
ちなみに、「パーティー」という言葉の語源は、ラテン語の「pars」や「partire」に由来しており、これらは「部分」や「分ける」といった意味を持ちます。
そこから派生し、ある目的のために集まる「仲間」や「一行」、また社交的な「集まり」や「会」といった意味を持つ「party」という言葉が生まれたのだとされています。
日本ではロールプレイングゲーム等で、一緒に戦う仲間達などに関連して使われることも多いですね。
様々なパーティー文化
ディナーパーティー(晩餐会)
古代から中世にかけて、晩餐会は社会的な交流の場として非常に重要な役割を持つパーティーでした。
特に欧州において王族や貴族が主催する豪華な晩餐会は、地位や権力を象徴するイベントとして位置づけられおり、マナーやルールも厳格なものであったといいます。
多くの人がイメージするパーティーが、このディナーパーティーかもしれませんね。
現代では、フルコースが提供されるようなフォーマルなものから、ビュッフェ形式のカジュアルなものまで、多くの晩餐会が開催されています。
ティーパーティー(茶会)
お茶と軽い軽食を楽しむスタイルのパーティー。
アフタヌーンティーとも呼ばれることもあり、17世紀ごろのイギリスが発祥だとされています。
食事と食事の間が空きすぎることを解消するために生まれた習慣が、次第に社交的なイベントへと発展していったのだと言われています。
アフタヌーンティーには専門店も数多く存在しており、本格的なお茶会を気軽に楽しむことが出来ます。
ダンスパーティー(舞踏会)
多人数でダンスを楽しむ催し。
舞踏会については主に社交ダンスの場を指しており、フォーマルな装いやダンスを誘う際のマナーなど、格調高い振る舞いが求められます。
また、広い意味でのダンスパーティーとしては、欧米における学年末のダンスパーティー「プロム」や、クラブカルチャーにおけるダンスパーティーなども挙げられることがあります。
日本では競技としての社交ダンスの方が馴染みはあるかもしれませんね。
バースデーパーティー(誕生会、生誕祭)
生まれた日を記念し、祝うパーティー。
私たちには最も馴染み深いパーティーと言えるかもしれません。
西洋で18世紀以降に始まったそうですが、実は広く普及するようになったのは20世紀に入ってからなのだとか。
また、日本では誕生日を迎えた人がお祝いされることが一般的ですが、海外では誕生日の本人が主催となり日ごろの感謝を伝えるパーティーを行う文化もあるそうです。
レセプションパーティー
レセプションパーティーとは、ビジネスシーンなどで主に業界関係者を招待して行われる社交・交流のためのパーティーです。
主にホテルや貸会議室、貸ホールなどで行われ、立食形での開催が一般的です。
公的なパーティーであり、人脈形成や情報発信の場としての側面が強いですが、主催者や主催業界によってなカジュアルな内容も見られます。
ここでご紹介したパーティーはごく一部にすぎません。
他にも、飲み物が中心の「カクテルパーティー」、屋外や庭園で開催される「ガーデンパーティー」、個人的な集まりである「ホームパーティー」など、様々なパーティー文化が存在しています。
人が集まる機会があれば、それはパーティーなのかもしれません。
また、その地域ならではのパーティーなんてものもある様なので、機会があれば調べてみても面白いかもしませんね。
小話:意外と知らない?パーティーの雑学
忘年会や新年会、実は日本だけって本当?
 日本ならではのパーティー文化と言われているのが忘年会・新年会です。
日本ならではのパーティー文化と言われているのが忘年会・新年会です。
仕事納めや新年のスタートを祝うこれらの会は、ビジネスシーンにも深く根付いていますが、実は海外では日本ほど重要視されていないことをご存知でしょうか?
近しい意味を持つパーティーは存在しており、アメリカの「ホリデーパーティー」、中国の「春節」、インドの「ディワリ」など、国や地域により様々です。
また、年末年始のカウントダウンは多くの地域で盛大にお祝いされています。
ただこれらのパーティーはプライベートで行われることが多く、日本の忘年会や新年会のように会社や組織が主体になって催されるパーティーはやはり日本独自の文化なのだそうです。
最近ではリモート参加やランチ会食のようなカジュアルな形式での開催も増えており、忘・新年会も時代に合わせて変化しています。
昔ながらのパーティーも良いですが、新しいスタイルを取り入れてみるもの良いかもせれませんね!
世界の様々な「乾杯」
 「乾杯」は、日本では宴席の始まりを彩る習慣です。
「乾杯」は、日本では宴席の始まりを彩る習慣です。
国ごとに表現や作法は異なり、英語圏では「Cheers! (健康のために!)」、フランスでは「Santé!(健康)」と掛け声を交わします。
また、中国では「干杯(ガンベイ)」といい、「杯を空にする」ほど飲み干すのが礼儀とされるのだとか。
ヨーロッパではグラスを合わせる際に目を見て乾杯することがマナーとされ、日本のように軽くグラスを合わせる所作は必ずしも一般的ではありません。
文化ごとの違いを知れば、国際的な場での乾杯もより楽しくなりますね。
ドレスコードの意味
 パーティーの招待状に「セミフォーマル」「スマートカジュアル」など、ドレスコードの表記がある場合はそれに従った装いが必要です。
パーティーの招待状に「セミフォーマル」「スマートカジュアル」など、ドレスコードの表記がある場合はそれに従った装いが必要です。
これらは、参加者全員が同じトーンで集うための主催側の配慮でもあります。
また「平服でおこしください」と書かれている場合でも、イベントの趣旨に合わせて服装を選ぶことがマナーとされています。
※平服=普段着ではないので注意が必要です。
ドレスコードを正しく理解し、TPOにあった服装選びができるよう心がけましょう。
現代のパーティー事情と未来
多様化する社会と共にパーティーのあり方も変化を続けています。
近年は、従来のパーティースタイルはもちろん、参加型・体験型のパーティーや、テクノロジーを活用したデジタル・バーチャルのパーティー、SDGsやサステナビリティといった観点から環境に配慮したパーティーや、異なる文化を取り入れた異文化交流型のパーティーなど多様な進化を遂げています。
また、大規模なパーティーでは難しい内容も、条件を絞ることで実現可能な場合もあり、使途に合わせた会場・業者選定などがより重要になっていると言えます。
わたしたちコルドンブルーでも、大小様々なパーティーの実績がございます。
国際的なレセプションなども数多く対応させていただいているので、パーティー・ケータリングでお困りの際には是非お気軽にお問い合わせください。
◆MENUはこちら
◆実施例はこちら
おわりに
パーティーとは、ただの「集まり」ではなく、文化、歴史、そして人と人との関係を育む貴重な場です。
その場をより豊かに楽しむためにも、ちょっとした知識やマナー、背景を知っておくことは大切かもしれません。
次に誰かとテーブルを囲むときは、こうした雑学をそっと披露してみてはいかがでしょうか?
会話が弾めば、パーティーの思い出はきっと素敵なものになることでしょう。

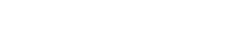









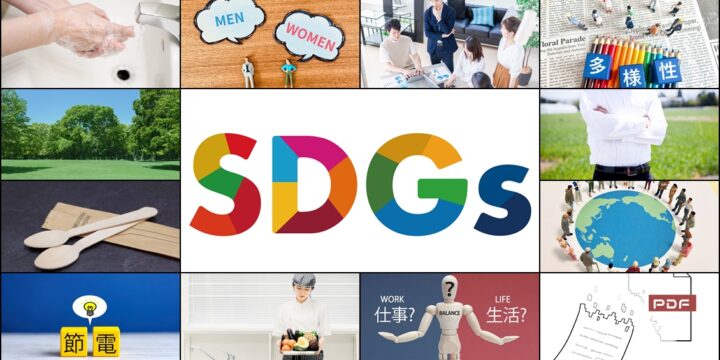


この記事へのコメントはありません。