梅雨の気象病にご用心 ~押さえておきたい6つのポイント~
毎年6月から7月にかけて、日本列島には「梅雨(つゆ)」が訪れます。
シトシトと降り続く雨、湿度の高さ、気温の変化、そしてどんよりとした曇り空。
この季節特有の気象の変化が、心と身体に影響を与えることを皆さんはご存知でしょうか。
近年では「気象病(きしょうびょう)」という言葉も徐々に認知されるようになり、特に梅雨の時期に体調不良を訴える人は増加の傾向にあるそうです。
今回は、そんな梅雨と気象病の関係やその特徴、そして予防・対策について解説していきたいと思います。
目次
気象病とは?
気象病とは、気圧や気温、湿度などの気象の変化によって体に不調が現れる状態のことを指します。
医学的には「天気痛(てんきつう)」や「気圧過敏症」とも呼ばれることがあります。
時々ドラマなどで耳にする“雨の日に古傷が痛む”といったセリフ、この症状も気象病の一種と言えます。
このような症状は、耳の奥にある「内耳(ないじ)」という器官の働きが影響していると言われています。
「内耳」は、音を感知するほか、体のバランスを保つ役割も担っています。
また、気圧の変化を感知するセンサーのような働きもしており、低気圧の影響を受けると自律神経のバランスが乱れて、頭痛、めまい、耳鳴りなどさまざまはな不調が現れることがあります。
梅雨に多い気象病の症状
梅雨の時期は、低気圧と高湿度が頻繁に訪れるため、気象病の症状が出やすくなります。
特に多く見られる症状としては以下の症状が挙げられます。
-
頭痛
梅雨時は偏頭痛や緊張型頭痛が悪化する人が多くいます。
これには低気圧が影響しており、体外から圧力が減ることで脳の血管が拡張しやすくなることが原因です。
拡張した血管は神経を圧迫し、頭痛が生じるとされています。
-
めまい・耳鳴り
内耳は気圧の変化に非常に敏感なため、低気圧の影響を強く受けてしまいます。
その結果、平衡感覚が乱れ、めまいや耳鳴りといった不調を感じることがあります。
-
関節痛・神経痛
リウマチや坐骨神経痛などを持つ人は、梅雨時に痛みが強まることがあります。
自律神経の乱れや、低気圧により体内の血流が滞り神経を圧迫しやすくなる事などが原因だと考えられています。
-
倦怠感・気分の落ち込み
日照時間が少なく、ジメジメとした空気が続くことで、心の状態にも影響が出ます。
ホルモンバランスが崩れ、気分の落ち込みやイライラ、うつ状態に似た症状を訴える人も少なくありません。
なぜ梅雨に体調が崩れやすいのか?
-
自律神経の乱れ
気圧の変化により、交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、身体の調節機能がうまく働かなくなります。
その結果、疲れやすくなったり、眠りが浅くなったりするなどの不調が生じます。
-
気温と湿度の影響
湿度が高くなると汗が蒸発しにくくなり、体温調節が難しくなります。
また、室内外の温度差が大きいと、身体の調整機能である自律神経に負担がかかり身体にだるさを感じるようになります。
-
日照不足
梅雨時は太陽の光が減るため、脳内で生成される「セロトニン」というホルモン(通称『幸せホルモン』)の分泌が少なくなり、気分が沈みやすくなるとされています。
気象病への対策と予防~押さえておきたい6つのポイント~
では、気象病を防ぐためにはどのような対策が効果的なのでしょうか。
日常生活の中からできる、押さえておきたい6つのポイントをご紹介します。
-
規則正しい生活を心がける
自律神経のバランスを整えるために、規則正しい生活を心がけましょう。
毎日決まった時間に起き、特に朝日を浴びることで体内時計が整いやすくなります。
夜も夜更かしはぜず十分な睡眠を心がけましょう。
2. バランスの取れた食事
塩分や脂質、糖質の摂りすぎは身体に悪影響を及ぼす可能性があります。
食物繊維やビタミン、ミネラルをバランス良く取れるよう献立を考えるようにしましょう。
間食もスナック類はなるべく控え、ナッツやドライフルーツなどを取り入れることで無理なく対策が可能です。
また、一日の食事リズムを整えることも重要です。
特に朝食をきちんと摂ることで、1日のスタートをスムーズに切れるため、血糖値も安定します。
-
軽い運動を習慣にする
ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、無理のない運動は血流を促進し、気象病の予防に効果的です。
天気が悪い日は室内でできる運動でも十分です。
また、運動した際にはこまめな水分補強も欠かさないよう注意しましょう。
-
耳を温める・マッサージする
内耳の血流を良くするために、耳を温めたり、軽くマッサージしたりすることが推奨されています。
耳の後ろを指で円を描くようにマッサージすると、リラックス効果も得られます。
最近ではマスクを着けている人も多いため、疲れを感じたら外してみるのも良いかもしれません。
-
湿度と室温を適切に保つ
エアコンや除湿機を活用して、室内の湿度を50〜60%、室温は22〜26度程度に保つと快適に過ごせます。
出先などで調整が難しい場合は羽織ものなどで調整できるようにするとよいです。
-
気象予報アプリを活用する
最近では、気圧の変化を通知してくれるアプリも登場しています。
事前にチェックしておくことで、体調不良のタイミングを把握しやすくなり対策ができます。
まとめ
梅雨の季節は自然と体に負担がかかる時期ですが、気象病を理解し、適切な対策を講じることで、可能な限り快適に過ごすことができます。
無理をせず、自分の身体と相談しながら少しずつ改善していくことが大切です。
もしも症状が長引く場合や日常生活に支障が出る場合は、早めに医師に相談することも検討しましょう。
健康的な梅雨の過ごし方を心がけ、心身ともに穏やかな季節を迎えましょう。
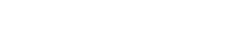











この記事へのコメントはありません。